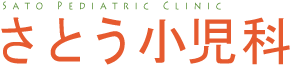今年の1月に、日本小児科医会から新しいポスター『保護者の方へ デジタル社会の子育て「幼児期に大切なこと」』が発表されました。
私もこのポスターの製作に携わらせていただきました。
長年、子どもに関わっている方たちの中には、「昔と子どもたちがかわってきた」と感じでいる方も多いのではないでしょうか?
要因は様々あるかと思いますが、私は「子どもたちの育ちが妨げられているのではないか?」との思いを長年持ち続けてきまし健診時にプリントアウトしたものを渡しています。
ご興味がある方は、日本小児科医会のHPからダウンロードして下さい。
幼児期は乳児期に引き続き、心や体が発育する大切な時期です。
この時期に「大切なこと」として「遊び」「生活リズム」「目」「会話」をあげています。
いずれも子どもの健全な育ちに「大切なこと」です。
当院では、1歳健診時にプリントアウトしたものを渡しています。
ご興味がある方は、日本小児科学会のHPからダウンロードして下さい。