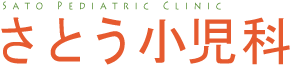あけましておめでとうございます。
本年も佐藤小児科をどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年は診察室での診療に加え、私が取り組んでいる「院外での活動」を皆さまに積極的にアピールする年にしたいと考えています。
私は現在、日本外来小児科学会や日本小児科医会、宮崎市郡医師会などで理事を務めるほか、2024年からは「NPO子どもとメディア」の活動にも深く携わっています。
学会では教育関係の委員会で次世代の医療向上に努め、医会では「子どもの心対策」やメディアとの付き合い方など、全国規模の仕組み作りに注力しています。
普段の宮崎での活動に加え、今後はこうした全国的な舞台での取り組みについても、皆さまにもご紹介していく予定です。
外での活動で得た最新の知見を日々の診察に還元し、子どもたちの笑顔を守る糧にしてまいります。
本年も温かく見守っていただければ幸いです。