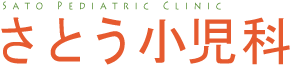最近では子育ての様々なシーンで使えるアプリが次々と登場しています。
24時間子どもと向き合わなくてならない親たちにとってはありがたいアプリでもありますが、そのスマホが子どもに与える様々な影響について考えてみました。
◎ 睡眠障害と集中力の低下
スマホなど電子端末の明るい光は、眠る際に必要なホルモン「メラトニン」の生成を阻害します。その為に眠りが浅くなったり、不眠になる可能性が高くなるといわれています。また、睡眠障害でセロトニンという脳内物質が減少すると、集中力の低下やイライラがちになるといわれています。
◎ 中傷・いじめ
最近は、無料アプリ内のグループなどで「はずし」と呼ばれる、グループから排除し仲間はずれにする事例や、ターゲットを招待しては退会させる事例が増えてきています。子どもは手加減を知りません。重大な事態になるまで放置されているケースが多いようです。
◎ コミュニケーション能力の低下
コミュニケーション能力は、表情や声のトーンなどをフルに活用し自分の言葉で相手に伝え、相手の気持ちを読み取る能力です。 スマホに集中し会話が少なくなることで、いざ人と向かって話をする時にコミュニケーションのとり方が分からず社会性の低下につながります。
◎ 言葉の発達の遅れ
スマホに頼って育児をしていると、子どもとのコミュニケーションが極端に減ってしまいます。特に言葉を覚えてお喋りをする時期に与えてしまうと、親との会話がない分、言葉の習得が遅れがちになります。
◎ 視力の低下
スマホやタブレットの画面からは ブルーライトという光線がでています。子どもの目はまだ発達途中で未熟な為この光線によって角膜や網膜を傷つけるといわれています。
◎ 依 存
スマホやタブレットは一方的に映像が流れるテレビとは違い、自分の指で画面が変わったり、動いたりするので子どもにとってはおもちゃと同じです。自分の行動に答えてくれるので依存性が高くなってしまいます。
子どものスマホ依存は保護者からの影響があります。
保護者の方はスマホに依存していませんか?
是非、チェックしてみて下さい!!
□ 寝る時、必ずスマホを枕元に置いて寝る。
□ 食事中でもスマホを見ることが習慣になっている。
□ トイレに行く時、必ずスマホを持っていく。
□ 入浴の際、脱衣所に必ずスマホを置いている。
□ 車を運転する際、バックの中からスマホを取り出し、必ず身近に置いている。
□ 人と話をしている時も、スマホを扱うことが多い。
□ スマホが身近に無いと、とても不安になる。
□ 近くにいる人のスマホが鳴った際、自分のスマホかと思いすぐにスマホを見てしまう。
□ スマホを使ってSNSを毎日必ずチェックしている。
□ 歩行している時も、スマホを持ち歩きチェックしている。
【 結 果 】
0個 オールフリー
1~2個 スマホ依存予備軍
3~4個 依存レベル 軽
5~7個 依存レベル 中
8個以上 重症
スマホは今ではなくてはならないものの1つになってきています。
悪影響だがらといって完全に断ってしまうのでは なく、怖さも知りつつ正しい使い方を知って与えるようにしましょう。
小さい頃からその正しい使い方を知っていれば、将来的にも依存することなく過ごすことが出来るかもしれませんね。