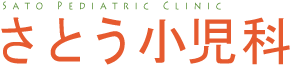今回は、私が業務担当理事を務めております「子どもの心対策委員会」の活動をご紹介します。
当委員会の主な役割は、毎年開催される「子どもの心研修会」(前期・後期)および「思春期の臨床講習会」のプログラム作成です。
全国各ブロックの委員から推薦された講師や書籍の情報を基に、内容を検討していきます。
推薦いただく講師や書籍はいずれも素晴らしく、選定時期には連日、書籍の精読やYouTubeの視聴に追われます。
「どの方に登壇いただくべきか」と頭を悩ませる日々ですが、それは非常に充実した時間でもあります。
2年前の診療報酬改定では、かかりつけ小児科医の役割として「発達障害の疑いがある患者への診療・相談、および専門医療機関への紹介」が明記されました。
その際、「適切な研修」のひとつとして当会の「子どもの心研修会」が挙げられています。
今後も、全国の小児科医の皆様の力となれるよう、質の高いプログラムを作成してまいりたいと思います。