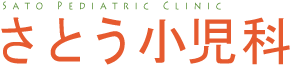今回、テーマに選んだのは「産後クライシス」。
これは、夫婦関係の話題で最初に選ぶテーマとしては不適切かもしれませんが、敢えてこのテーマを選んだのは、“夫婦仲は子供の将来に大きく影響を与する”からです。
「産後クライシス」という言葉は、2012年にNHKが提唱した言葉で、「出産から子どもが2歳ぐらいまでの間に、夫婦の愛情が急速に冷え込む現象」を指し、実際、母子家庭の約30%は、末子が2歳未満で離婚しています。
なぜこのようなことが起きるのか?
それは、出産の前後での女性の体内での内分泌学的変化が原因と考えられています。
女性は、出産の前後で「オキシトシン」というホルモンが多く分泌されます。
オキシトシンの生理的作用は、分娩促進や乳汁分泌促進になりますが、近、このオキシトシンが脳に作用していることが分かってきました。
オキシトシンは、我が子やパートナーへ愛情を強める働きがあり、「愛情ホルモン」「絆ホルモン」といわれることもあります。
しかし、「他者への攻撃性」を強める作用もあります。
これは、本来、子どもを外敵から守るためと考えられていますが、女性の場合、育児に非協力的な人は「攻撃の対象」となり、女性のイライラ感が強められる原因となるのです。
さて、我が家はといいますと、お産の陣痛で妻が痛がっている際、冗談混じりで妻を励ましていましたが、ある瞬間“これ以上言うと一生恨むぞ”という目つきで私を睨みました。
まさに、オキシトシンが大量に分泌され攻撃性が顔を出した瞬間を私は体験しました。
それから私は、お産が終るまで数時間、一言も言葉を発しませんでした。
先日、知り合いの弁護士の先生と出産前後の女性の話をしていた時、「夫婦問題の相談を受けると、特に女性の場合は、出産時の夫の行動を非難するケースが少なくないです。」という話を聞きました。
私の母も出産の際の父の行動を未だに鮮明に覚えているようです。
オキシトシンは出産前後の嫌な記憶を増強する作用もあるようです。
女性は出産を契機に必ず変わります。
生物学的に「お母さん」になるということはそういうことなのです。
私が今回、皆さんにお伝えしたいことは、それでも子供が生まれたからには、その子供が健全に育つため子供を中心においた話を御両親でして欲しい、そのためにはお互い協力できるところは協力していただきたい、ということを記して今回の話を終わりにしたいと思います。